
ふるさと館近況・よもやま話
・満天の星空を見あげると心がときめくのは何故?
・月のクレーターや土星の輪を望遠鏡で覗いたとき、みんな歓声をあげるのは何故?
・多くの天文学者たちが宇宙の謎を追究し続けてきたのは何故?
・「はやぶさ2」など多くの宇宙船や探査機が、はるかな宇宙を目指すのは何故?
「宇宙」は限りないロマンと、知り尽くすことができない多くの謎に満ちています。
「ふるさと館近況・よもやま話」では、「星」や「宇宙」に関する話題、
「星のふるさと館」のイベントの様子など、「星空や星のふるさと館」に
興味を感じていただけるような話題をお知らせしていきます。
ときどき更新します。よろしくお願いいたします。
上越清里星のふるさと館 館長 松野和美(R4.4〜)
令和4年9月10日(土)
星のふるさと館では、「天体写真に挑戦」の講座を1年間に8回実施しています。
年度当初に募集を行い、初級と中級の2グループで運営しています。講義、情報交換、
撮影の計8回の講座を通して、楽しみながら天体写真に挑戦しています。
写真は、第6回目(8月28日)の「光ヶ原高原で天体写真に挑戦」の様子です。
雨の翌日で、とても空気が澄んでいました。撮影の前半は雲間に星空が見える状況
でしたが、後半は雲がほとんど無くなり、美しい星空を楽しむことができました。
天頂付近には「天の川」と「夏の大三角」、低高度には「秋の四辺形」
「アンドロメダ銀河」「木星」「土星」が昇ってきています。手前の赤い光周辺は、
中級の方が望遠鏡を使って撮影を行っているところです。
標高約500mの星のふるさと館では、一足先に秋の気配が感じられる頃となってい
ます。写真にもあるように、夏の星座や秋の星座、さらに土星や木星が見ごろの時季です。
金曜・土曜の夜には観望会を実施しています。ぜひ、秋の夜空を「星のふるさと館」でお
楽しみいただければと思います。天候により、観望会は中止となります。実施の有無は、
当日の16時以降にお電話でご確認をお願いいたします。
 |
令和4年8月7日(日)
上越市立青少年文化センター(上越市国府:2013年3月閉館)をご存じの方も
多いと思います。目が光るロボットや鉄道ジオラマなど、私も懐かしく思い出す
ことができます。この青少年文化センターの閉館にあたり、「ある展示物」が
星のふるさと館に移され保管されてきました。そして9年後の今年7月から、
再展示を開始しました。
「ある展示物」とは、当時は「ケプラーの法則説明モデル」でした。この名前で、
思い出される方はなかなかの宇宙好きといってよいと思います。「鉄球がグルグル
回りながら、中心の穴に向かってどんどん速く回り、ついには中心のへこんだ穴に
ゴロンと落ちる展示物」と聞くと、懐かしく思い出される方が多いと思います。
この「ケプラーの法則説明モデル」が星のふるさと館で「ブラックホールモデル」
として再び活躍してくれています。当時は電動で、スタートボタンを押すと鉄球が
内部で運び上げられ、自動的に鉄球が転がり込む仕組でした。現在は手動で、手で
鉄球を持ち上げて投入口に入れることで転がり込みます。この後の動きは当時と同様
ですが、中心の穴をブラックホールに見立て、ブラックホールに吸い込まれていく
様子を見るモデルとしています。手動ですので、連続して鉄球を入れたり、重さの
違う鉄球を入れたりして、その様子を予想しながら楽しむ事ができます。また、光
さえも出られない実際のブラックホールと違い、落ち込んだ鉄球は下からゴロンと
出てきます(当たり前ですね)ので、何度でも試してみることができます。子ども
から大人まで、結構楽しんでいただいています。
2019年4月に、世界初のブラックホール画像(M87銀河中心)が公開されました。
2022年5月には、私たちが住む天の川銀河の中心にある巨大ブラックホール、
いて座A*の姿を初めて捉えた画像が公開されました(画像としては異論もあるよう
ですが)。現在の天文学ではブラックホールの存在は当たり前となっており、
さらには様々な天文現象の説明に重要な役割を果たしていると考えられています。
8月は、天の川や夏の星座を観察する好機です。子どもたちの夏休みやお盆休み等
があるこの時期は、「星のふるさと館」は休館日なしでいろいろなイベントを
計画しています(8月28日まで)。多くの皆様に宇宙に関わる楽しさを体感して
いただきたく、皆様のご来館をお待ちしております。

令和4年6月22日(水)
今年の夏至(夜が最も短い日)は6月21日でした。日没後も空には明るさが残り、
肉眼で見える6等星までが夜空に光り始める時刻も21時少し前となっています。
夜が短い季節となっていますが、夜の涼しさを感じながら夜空を眺める事の
できるこの頃です。
この時季の21時頃に夜空を見上げると、春の星座が天球の西側半分に傾き、
夏の星座が天球の東側半分に昇ってきています。「春の大曲線」と夏の「天の川」が、
春から夏への季節の移り変わりを感じさてくれます。この星座の移り変わりは、毎年
同じタイミングで繰り返されています。ところが、惑星の見え方は年によって大きく
異なります。今年のこの時季の21時頃の夜空には、明るく輝く「惑星」が見られません。
しかし、夜半から朝方にかけて、太陽系の全ての惑星が日の出前に次々と東から
昇ってきます。最初に昇って来るのは土星で22時30分頃、その後に土星、海王星、
木星、火星、天王星、金星、そして最後に水星が3時30分頃に昇ってきます。5時間
ほどの間に、惑星が接近している状態はとても希なことです。ぜひ3時頃に東の空を
見ていただくか、星のふるさと館のプラネタリウムでその様子を見ていただくかして、
今年のこの時期の星空チャンスを楽しんでいただければと思います。
 |
話は変わりますが、小惑星探査機「はやぶさ2」が持ち帰った小惑星「りゅうぐう」
から持ち帰った「岩石サンプル」から、グルタミン酸などのアミノ酸が23種類も発見
されたというニュースが6月10日にありました。同時に、水の存在もアミノ酸合成の
根拠として確かなものと考えられています。地球は、水や有機物に恵まれた貴重な
環境であることには変わりありませんが、「地球外にもこれらはたくさんある」と
いうことが当たり前の時代になっています。
星のふるさと館では、「はやぶさ2」が持ち帰った「岩石サンプル」の実物大と
10倍の大きさのサンプルレプリカ(模型)を11月まで展示しています。
「はやぶさ2 2195日の軌跡」の短編動画とともに、お楽しみいただけます。
また、小惑星の1つに「Kushiike」(櫛池隕石が落下した地点名の櫛池)が命名されて
います。これに関わる展示も行っています。皆様のご来館をお待ちしております。
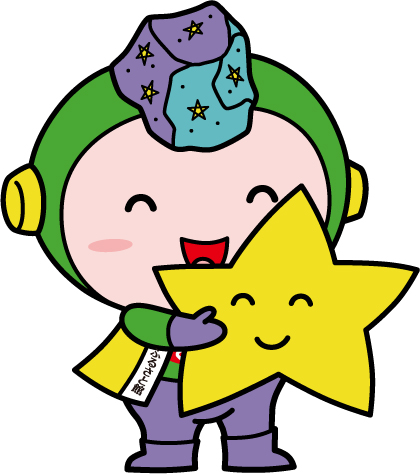 |
令和4年6月1日(水)
高田平野の水田も田植えが進み、水田の水鏡に夕焼けや夕日が映える頃となって
います(写真)。夏至(6/21)の頃には、夕日が能登半島の先端と日本海に沈んでいく
様子を星のふるさと館屋上から観察できるようです。
 |
星のふるさと館では、金曜日と土曜日の夜を基本として観望会を行っています。
5月27日(金)・28日(土)は晴天に恵まれ、とてもきれいな星空を観望することが
できました。市街地から車で30分ほどの星のふるさと館では、光害がほとんど無い
状態で夜空を眺めることができ、とても恵まれた星空環境にあると思います。
観望会は、19時〜22時(最終入館21:30、要入館券)に行っています。先日の観望会
では、夕暮れ時に西に沈んでゆく冬の星座、天頂付近まで昇っている春の星座、東から
昇ってくる夏の星座・天の川を観望できました。屋上の観望デッキでは、シートに寝転び
ながら肉眼や双眼鏡・望遠鏡で、星座や恒星さらに流れ星や飛行機・人工衛星の様子を楽
しむことができます。望遠鏡ドームでは、県内最大の望遠鏡等を使って、恒星の輝きや
星雲・星団の様子を観望していただくことが可能です。
4,5月には計21回の観望会を計画しました(連休中は毎日実施の計画でした)。
このうち、晴天で実施できたのは計9回(実施率43%)でした。実施の有無の判断は、
天気予報サイト「SCW」等で1時間ごとの雲予報を確認して、16時頃に行っています。
観望会実施日についてはホームページでご確認いただき、当日の観望会実施の有無に
つきましては電話で「星のふるさと館(025-528-7227)に確認をお願いいたします。
また観望会参加の際には、防寒着のご用意をしていただくと快適と思います。
 |
令和4年5月16日(月)
草木の萌黄色が力強い新緑へと濃さを増し、フジやホオノキの花が咲く頃となりました。
坊ヶ池に映る、青空・残雪の妙高山・木々の緑が、坊ヶ池の湖面に映えています。
 |
あまり黒点を見つけられませんでしたが、今年は黒点がたくさん発生していて、晴れていれば
毎日その様子を見ることができています。太陽の黒点の発生には11年の周期があります。
つまり、今年は11年ぶりに黒点増加の年を迎えていることになります。また、プロミネンスも
たくさん発生していて、その様子も観察することができます。
太陽の表面の様子を見るには、太陽からの光の一部分だけを通す特別なフィルターが必要です。
このフィルターと望遠鏡を使うと、拡大された太陽表面の黒点やプロミネンスの迫力のある様子を
見ることができます。
星のふるさと館の望遠鏡ドームには、このフィルターを付けた太陽観察専用の望遠鏡があります。
コンピュータで制御していますので、その様子を簡単に観察することができるようになっています。
ぜひ、今年の活発な太陽活動の様子を、星のふるさと館で実際に観察していただきたいと思います。
【注意】肉眼や双眼鏡・望遠鏡などでは、絶対に太陽を見ないようにしてください。